建設業における書類の保存期間と廃棄方法
このページでは、建設業法で定められている書類の保存期間について解説しています。知っておきたい書類を保存する必要性や書類ごとの保存期間、書類の管理、廃棄方法などをまとめていますので、ぜひお役立てください。
書類の保存期間は建設業法で定められている
建設業では工事発注の仕事が元請けから一次、二次受けへと続くピラミッド構造になっており、それぞれの業者間で見積もりや契約、請求などの工程を必要とするため、多くの書類が発生します。また、契約や検査をするにあたって、膨大な資料や図面も必要です。業務で取り扱う書類のほとんどに建設業法で保存期間が定められており、建設業許可を取得している建設業者には建設業法に基づく書類の保存が義務付けられています。
書類を正しく保存する必要性とは?
さまざまな種類の書類を取り扱う建設業ですが、膨大な書類の整理や保管場所に困っているからといって好き勝手に処分してはいけません。存期間を守らなかった場合に発生する問題に注目しながら、書類を正しく保存する必要性について見ていきましょう。
法令違反になる可能性がある
建設業法で、「国土交通大臣と都道府県知事は、必要に応じて建設業者の財産、工事の状況、帳簿書類、その他の物件を検査させることができる」と規定されています。何らかの問題が発生して書類の提出を求められた際に、保存期間を守らずに書類を処分してしまっていた場合、法令違反として罰金を取られる可能性があります。
労働災害が発生したときの手続きに必要
高所での作業や重機の使用も多い建築現場では、事故が発生するリスクが他の職種よりもかなり高くなっています。また、長時間大きな音にさらされるため、職業性難聴の発生率も高い職種です。労働環境が原因で発生する病気のなかにはすぐに症状が出ないものもあり、労災として申請するにはその現場で従事していたことを証明する書類の提出が求められます。
つまり、書類の適切な保存は、従業員の安心・安全を守ることにもつながるのです。
施工後のトラブル時に必要
建設業では施工後に業者間で金銭トラブルが発生することがあります。このときに書類を正しく保存していれば、契約に基づいて適正に施工がされた証明として裁判で争うことになった際の武器となります。一方で、必要な書類を処分してしまっていた場合は、責任を問われて大きな問題に発展しかねません。
会社や従業員を守るためにも、書類の保存期間をしっかりと把握して正しく保存する必要があるのです。
建設業法で保存期間が定められた書類一覧
建設業法で定められている保存期間は書類によって異なるため、書類の整理や保存をするにあたってややこしく感じている人もいるでしょう。適切な保存・管理の参考になるように、保存期間別に書類をまとめました。
3年保存
- 安全衛生委員会議事録
- 特別教育の記録
- 騒音測定記録
- クレーン過負荷制限特例記録・デリック過負荷制限特例記録
- クレーン点検記録・デリック点検記録・エレベーター点検記録
- 移動式クレーン点検記録・簡易リフト点検記録
- 建設用リフト点検記録
- 有機溶剤作業環境測定記録
- 有機溶剤作業環境測定結果の評価記録
- 鉛作業環境測定記録
- 鉛作業環境測定結果の評価記録
- 特定化学物質用局所排気装置・除じん装置・排ガス処理装置・廃液処理装置点検記録・特定化学設備またはその付属設備点検記録
- 特定化学物質作業環境測定記録
- 特定化学物質作業環境測定結果の評価記録
- 酸素欠乏危険作業場所環境測定記録
- 粉じん用局所排気装置および除じん装置点検記録
5年保存
- 帳簿
- 帳簿の添付書類(契約書、下請負人に支払った下請代金の額、支払年月日及び支払手段を証明する書類又はその写し、施工体制台帳)
- 健康診断個人票
- 有機溶剤健康診断個人票
- 鉛健康診断個人票
- 四アルキル鉛健康診断個人票
- 特定化学物質等健康診断個人票(特別管理物質は30年間)
- 放射性物質濃度測定記録
7年保存
- 粉じん作業環境測定記録
- 粉じん作業環境測定結果の評価記録
10年保存
- 営業に関する図書(工事内容に関する発注者との打ち合わせ記録、完成図、施工体系図)
30年保存
- 特別管理物質製造・取扱作業記録
- 特定化学物質等健康診断個人票(特別管理物質のみ)
- 電離放射線健康診断個人票
保存期間なし
- 衛生日誌・衛生管理者の職務上(巡視等)の記録
- 産業医の職務上(巡視等)の記録
書類はどのように整理したら良いの?
書類ごとの保存期間を把握したら、次に考えなければいけないのが膨大な書類の整理方法です。効率よく書類を整理するための方法や保存期間の経過後も保管しておきたい書類を紹介します。
案件別・保存期間別に分類する
まずは必要になったときに書類をすぐ取り出せるよう、案件ごとに分類しましょう。案件ごとにファイルをまとめ、さらに日付順に並べておけば、過去の案件で問題が起きたときに必要な書類をすぐ取り出すことができます。案件別で大まかに分けたら、次は保存期間別にファイルをまとめていきます。そうすることで保存期間が過ぎた書類を判別しやすくなるため、書類の管理が楽になるでしょう。
保存期間によらず保管しておいたほうがよい書類
建設業許可を取得・更新する際、営業所ごとに経営業務の管理責任者が必要です。経営業務の管理責任者を設定するには、経営経験を証明する過去の注文書や請求書などの書類が求められます。保存期間が経過したからと申請に必要な書類を破棄していた場合、経営経験を証明する書類の不備を指摘される可能性があります。
そのため、これらの書類は保存期間によらず、10年は保管しておくと良いでしょう。
保存期間が過ぎたら廃棄してもいいの?
建設業法で定められている保存期間が過ぎた書類については、廃棄しても法律的には問題ありません。
ただし、書類によっては保存期間の経過後も保管しておいたほうがよいものもあります。一方で、マイナンバーが記載されている書類などは保存期間が過ぎたら速やかに廃棄すべき書類です。建設業法で定められている保存期間は守りつつも、廃棄するタイミングについては書類ごとに検討する必要があるでしょう。
まとめ
機密文書を廃棄する際、個人情報や機密情報が漏えいしないように廃棄する必要があります。処理方法として一般的なのが、シュレッダーによる廃棄です。ただ、大量の書類をシュレッダーで処理するとなるとかなりの時間がかかるほか、その分の人件費も発生します。また、シュレッダーによる裁断は復元できる可能性もあるため、機密情報を完全に抹消できる手段ではありません。
セキュリティ面を重視するのであれば、専門の業者に依頼する選択肢も視野に入れておくと良いでしょう。業者によって信頼性や安全性に差があるので、回収や運搬時のセキュリティ対策がしっかりと講じられているか、情報漏えい事故を起こしていないか、情報保護やセキュリティにかんする認証を取得しているかなどを確認することをおすすめします。
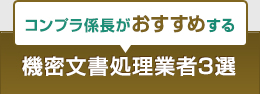
-
日本シュレッダーサービス
1,980円~ -
T-CUBE
(竹下産業)
2,200円~ -
デルエフ
1,078円~
※関東限定
- 日本シュレッダーサービス
- 要興業
- 日本郵便
- テルヰ
- 美濃紙業
- デルエフ
- ヤマト運輸
- 日本パープル 保護くん
- 株式会社ワラケン
- 大塚商会
- 西濃運輸
- 日本通運
- 東武デリバリー
- エコモーション
- 小田商事
- 佐川急便
- ワタコー
- 買取王子
- けすぷろ
- NTTロジスコ
- WELL
- 永田紙業
- 竹下産業
- 上山商事
- 機密文書出張細断(旧エコシュレッドサービス)
- アサヒ・クリーン
- SRI(株式会社セキュリティリサイクル研究所)
- 東京レコードマネジメント株式会社
- 山崎文栄堂
- ALSOK(綜合警備保障株式会社)
- 奥富興産
- 栗原紙材
- 大和紙料
- ナカバヤシ
- 王子マテリア
- リサイクル・ネットワーク
- シオザワ(リンクル事業部)
- 開発紙業
- リパック
- ふじ産業
- 大阪紙業
- 株式会社KNP
- 丸升増田本店
- リーガルサービス
- セキュリティソリューション
- 寺田倉庫
- 環境整備産業
- 紙資源
- 株式会社シマダ
- 増田喜
- 山本清掃
- キーペックス
- 近江美研
- ケア・イノベーション
- ライオンロジスティクス
- 車谷

コンプラ係長
社内でコンプライアンス関連の業務に携わっています。書類の処理について、いつも口うるさく言っているので、周りからはコンプラ係長と呼ばれています(笑) いま、適切な情報漏えい対策をすることが、企業の課題になっていると思います。メールや外部メモリーなど、情報漏洩の原因は様々ですが、実は紙(書類)からの漏洩が7割を占めているのです。 社内から情報が漏れて信用問題にならないよう、早めに機密文書の廃棄業者を手配しておきましょう。
【免責事項】
このサイトは、コンプラ係長を擁する編集チームが各社の公式情報を中心に情報を集めて制作しています(2019年12月時点)。機密文書処理業者の情報などは、必ず各公式ホームページなどで確認してください。
